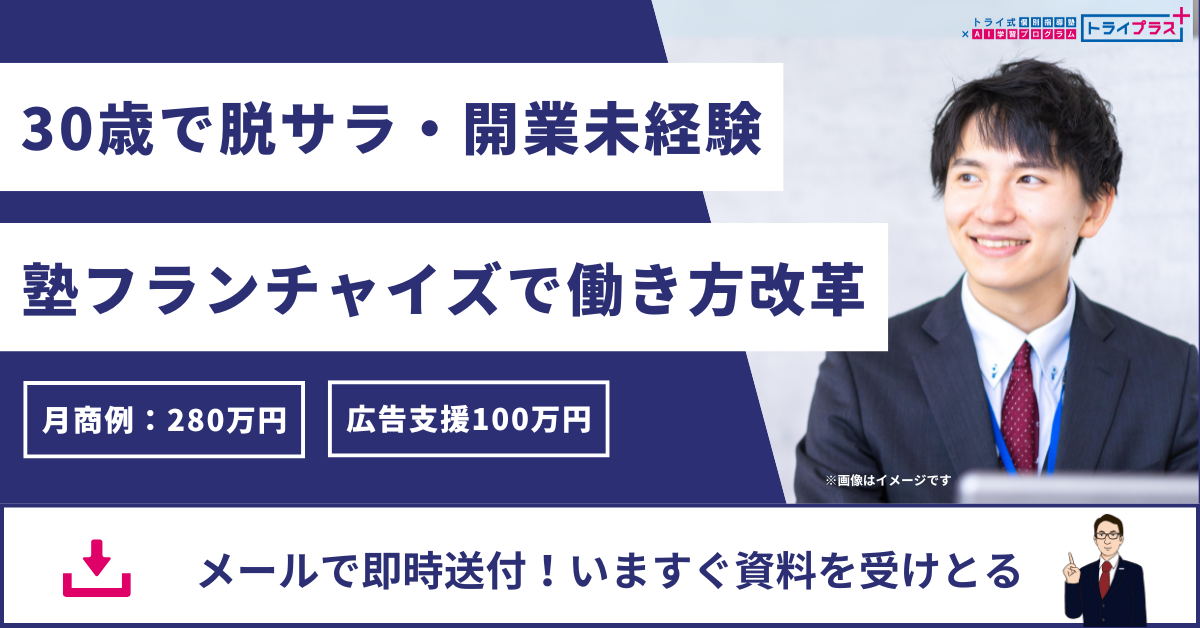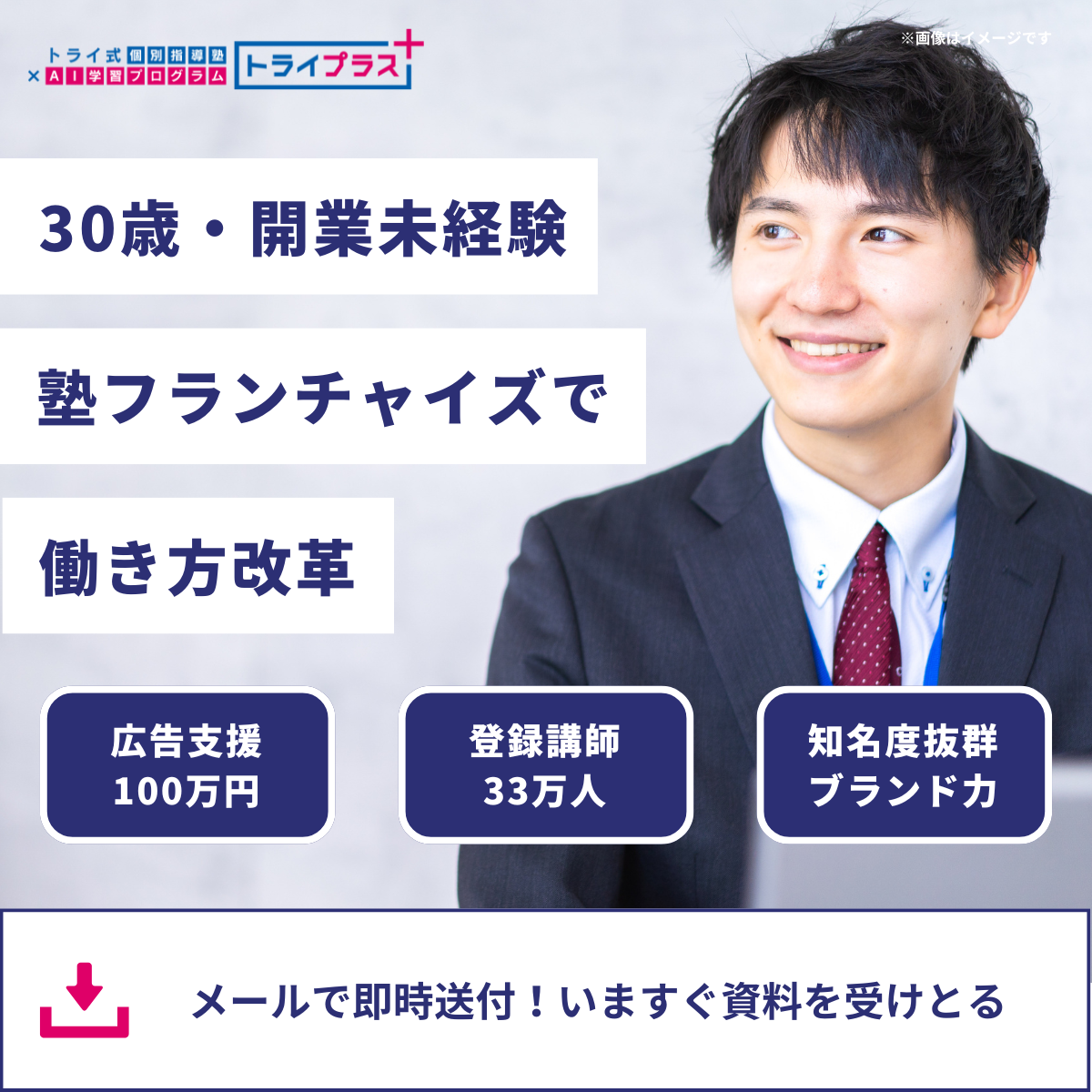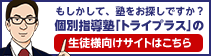塾の生徒が集まらない!原因やまずやるべき効果的な方法を紹介
塾経営において「生徒が集まらない」という課題は、多くの塾長や経営者が直面する重要な問題。
「良い教育を提供しているのに生徒が増えない」「広告を出しても反応が悪い」など、様々な悩みを抱えている方も多いでしょう。
生徒が集まらない原因は、「認知されていない」「魅力が伝わっていない」「体験後の入塾につながらない」という3つの段階に分類できます。
本記事では、それぞれの課題に対する具体的な対策方法と、塾経営を成功に導くためのポイントについて、詳しく解説していきます。
- 塾に生徒が集まらない原因
- まずしておくべき集客施策
- 塾の生徒を増やす方法(原因別)
- 生徒集めに適した時期
- 生徒が集まらず失敗してしまうケース
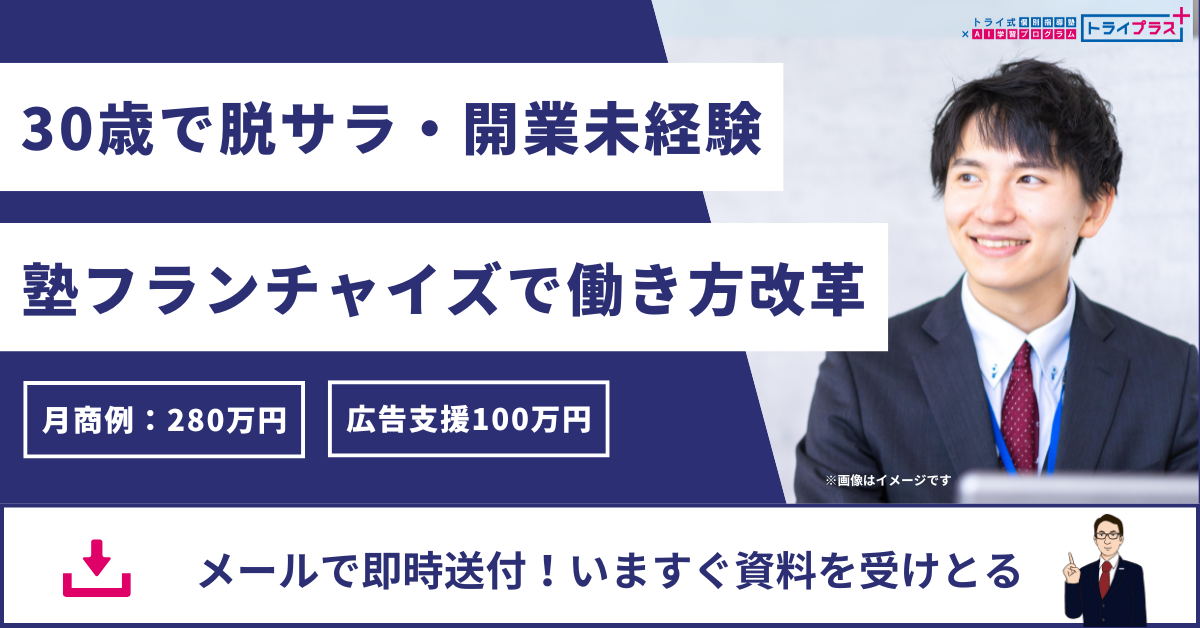
塾に生徒が集まらないのはなぜ?
生徒募集において、成果が上がらない原因は、顧客の行動プロセスに応じて大きく3つに分類できます。
まずは「認知」を獲得し、その後「魅力を感じてお問い合わせ」につなげ、最終的に「体験後の入塾」を実現するというフローが、塾に生徒を集める流れ。多くの塾がそれぞれの段階でつまずいているのです。
各段階の課題を正確に把握することで、効果的な対策を講じることができます。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
| 段階 | よくある課題 | 主な原因 |
| 認知獲得 | 地域での知名度不足 | ・広告展開が不十分
・立地条件が悪い ・情報発信が不足している |
| 問い合わせ | 反応・反響が少ない | ・特徴や強みが不明確
・競合との差別化が足りない ・訴求内容のミスマッチ |
| 入塾決定 | 体験後の成約率が低い | ・価値提案が不十分
・他塾との比較で見劣りしている ・保護者の不安を解消できていない |
理由1. そもそも認知されていない
多くの塾が直面する最初の壁が「認知」の問題です。いくら優れた指導方法や実績があっても、地域の保護者や生徒に知られていなければ選択肢にすら入りません。
特に新規開校の塾や、住宅街から少し離れた場所にある塾では、この課題が顕著です。
また、認知の質も重要な要素となります。単に「塾の存在を知っている」だけでなく、「どんな塾なのか」「どんな指導をしているのか」という基本的な情報が伝わっていないケースも多く見られます。
この場合、一瞬目に入っても記憶に留まらないため、結局忘れられてしまい、認知を失うことにつながります。
理由2. 認知はしているが魅力的だと感じていない
塾の存在は知られていても、問い合わせや体験授業の申し込みまで至らないケースも多く見られます。
塾の特徴や強みが効果的に伝わっていない、または競合との差別化ができていないことが主な原因です。
特に、「なぜこの塾を選ぶべきなのか」という魅力が伝わっていないことが大きな課題となっています。
例えば、「少人数制」「個別指導」といった表面的な特徴を掲げていても、それが実際に子どもの教育にどんな良いことをもたらすのか、具体的なメリットまで伝えきれていないケースが多く見られます。
また、地域内の競合塾と似たような訴求をしている場合、差別化要因として機能していない可能性も。
理由3. 問い合わせた後の入塾率が低い
実際に問い合わせた後に入塾に至らないケースは、最も改善の余地が大きい課題です。
これは塾の本質的な価値が伝わっていない、または競合と比較して選ばれる理由が明確でないことが原因で起きる問題です。
問い合わせ後は体験授業に繋げるケースが多いですが、体験授業は塾の教育方針や指導力、授業の雰囲気を直接示せる重要な機会。
しかし、単に授業を体験してもらうだけでは、入塾の決め手とはなりません。
保護者の不安や懸念を解消する、子どもの学習意欲を十分に引き出す、または料金面での納得を得る、これらを満たさなければ入塾に繋げることはできません。
塾の生徒を集めるためにまずやるべきこと
新規生徒の獲得には、複数の施策を組み合わせた総合的なアプローチが必要です。
特に開校初期や生徒数が伸び悩んでいる場合、以下の基本的な施策から着手することで、効果的な集客の基盤を作ることができます。
・チラシを配り地域からの認知を得る
・訴求を整理しホームページに記載する
・地図アプリなどで口コミ対策する
チラシを配り地域からの認知を得る
地域密着型の学習塾にとって、チラシ配布は依然として効果的な認知施策の一つ。
特に、通塾圏内(自転車で15分程度)の重点エリアでは、定期テスト前や長期休暇前など、タイミングを見計らった配布が重要です。
| 配布手法 | 適したエリア | 効果を高めるポイント |
| ポスティング | 住宅地域 | 定期的な配布で認知度向上 |
| 駅前配布 | 通学路沿い | 朝夕の通学時間に集中する |
| 個別投函 | 住宅地域 | 可能であれば手書きで |
作成するチラシには、単なる料金案内だけでなく、塾の特徴や実績、具体的な成功事例を盛り込み、読み手の関心を高めましょう。
訴求を整理しホームページに記載する
現代の保護者は、塾選びの際にはほぼ必ずホームページを確認します。
そのため、自塾の強みや特徴を明確に伝えるコンテンツ作りが重要に。
特に重視すべきは、「なぜこの塾を選ぶべきか」という差別化ポイントを明確にすることです。
| 掲載項目 | コンテンツのポイント |
| 指導方針 | 具体的な指導事例を交えて説明 |
| 講師紹介 | 経歴や指導実績を詳しく載せる |
| 実績 | 数値データとお客様の声を載せる |
写真や動画も効果的に活用し、塾の雰囲気や実際の指導風景を伝えることで、保護者の不安解消にもつながります。
地図アプリなどで口コミ対策する
昨今の塾選びでは、Google Maps等の地図アプリでの評価が大きな影響力を持ちます。
口コミ対策は、単に悪評がついてないかチェックする評価管理だけでなく、塾の魅力を伝える重要な機会として捉える必要があります。
| 対策項目 | 具体的な取り組み | 効果 |
| 基本情報 | 住所・連絡先・写真の最適化 | 信頼性向上 |
| 口コミ返信 | 丁寧な応対・詳細な説明 | 誠実さアピール |
| 情報更新 | イベントや実績の定期投稿 | 活気のアピール |
特に重要なのは、寄せられた口コミへの対応。
ポジティブな口コミはもちろん、改善要望などにも誠実に対応することで、塾の姿勢や特徴を効果的に伝えることができます。
体験授業を実施する
体験授業は、塾の質を直接感じてもらえる最も重要な機会。
ここでの体験が入塾の決め手となるため、通常授業以上の準備と工夫が必要です。
| フェーズ | 実施内容 | ポイント |
| 事前準備 | 生徒の現状・目標把握 | 個別にカリキュラムを設計する |
| 授業実施 | 実際に指導を行う | 成功体験を作ってあげる |
| 事後対応 | 保護者へ丁寧に説明する | 具体的な学習プランを提示する |
体験授業後は、生徒の様子や理解度を踏まえた具体的な学習プランを提案し、保護者の不安解消を図ることが重要です。
既存の生徒に紹介してもらう
既存生徒からの紹介は、確度の高い集客方法。
そのためには、まず現在通塾している生徒と保護者の満足度を高めることが不可欠です。
塾生以外を誘っても良い勉強会など、友人を誘いやすい機会を設けることで、自然な形での紹介を促進できます。
ただし過度な紹介依頼は鬱陶しいと思われ逆効果となる可能性があるため注意しましょう。
塾の生徒を増やす方法をケース別に紹介
生徒集めの課題は、塾の状況によって異なります。
ここでは、「認知度が低い」「応募が少ない」「入塾率が低い」という3つの典型的なケースに分けて、効果的な対策方法を解説していきます。
認知度が低い場合
新規開校や立地条件の影響で認知度に課題がある場合、まずは露出を増やすことが重要です。
効果的な認知向上策は以下の通りです。
- Web広告を出稿する
- 通学路などに看板を設置する
- 学校前でティッシュなどを配る
1. Web広告を出稿する
地域を絞ったWeb広告は、効率的な認知獲得の手段として有効です。
特にGoogle広告やSNS広告では、学習塾を検討している層への効果的なアプローチが可能です。
リスティング広告では、「〇〇市 学習塾」「中学受験 塾」といった具体的なキーワードで、すでに塾を探している層へ直接アプローチできます。
また、SNS広告では、子育て世代の保護者をターゲットにした認知施策が効果的です。
Instagramなどの画像主体のプラットフォームでは、実際の授業風景や生徒の成長事例を視覚的に訴求することで、塾の雰囲気や特徴を効果的に伝えることができます。
| 広告種別 | 主なターゲット | 訴求のポイント |
| 検索広告 | 塾探し中の層 | 地域性、特徴的な指導方針 |
| SNS広告 | 子育て世代全般 | 教室の雰囲気、生徒の声 |
| ディスプレイ広告 | 潜在層 | 認知度向上、ブランディング |
全体として広告運用では、季節性を考慮して予算を配分することが重要です。
定期テスト前や受験シーズンには予算を増額し、効果的な露出増加を図るようにしましょう。
2. 通学路などに看板を設置する
通学路への看板設置は、継続的な認知向上に効果的な施策。
特に学校から駅までの動線や、塾周辺の主要な通学路を狙って設置するのが良いでしょう。
看板は単なる位置案内だけでなく、塾の特徴や現在実施中のキャンペーンなども効果的に伝え、地域の中で存在感を示すことができます。
また、看板のデザインや設置場所によって効果は大きく異なります。
例えば、信号待ちで立ち止まりやすい交差点付近やバス停近くなど、生徒が自然と目にする場所を選択することで、認知効果を最大化できます。
3. 学校前でティッシュなどを配る
学校周辺でのティッシュ配布も、アプローチとして効果的です。
特に、定期テスト前や長期休暇前など、保護者や生徒の学習意欲が高まる時期での実施が重要です。
配布物の内容も重要で、単なる料金表やキャンペーン情報だけでなく、学習のヒントや受験情報など受け取った人が「保管したくなる」情報を盛り込むことで、より高い効果が期待できます。
効果的な配布のポイント
- 下校時間帯の16~18時に集中して実施する
- 保護者向け・生徒向けで内容を使い分ける
- 季節に応じた学習アドバイスを掲載する
- 体験授業への導線を記載する
認知度は高いはずだが応募が少ない場合
認知はされているものの問い合わせや申し込みが少ない状況は、情報発信と実際のニーズにミスマッチが生じているのが原因です。
この場合、広告などによる単なる認知向上ではなく、訴求内容の見直しや、申し込みへのハードルを下げる取り組みが必要となります。
以下の3つの方法を検討してみると良いでしょう。
- 認知された後の流れを整理する
- キャンペーンを実施する
- 体験授業・無料相談を実施する
4. 認知された後の流れを整理する
認知から申し込みまでの顧客導線を詳細に分析し、改善する点を突きとめましょう。
多くの場合、ホームページやチラシを見た後の行動に障壁が存在します。
例えば、問い合わせフォームが複雑すぎる、電話受付時間が限られている、といった些細な要因が申し込みの妨げとなっていることがあります。
特に重要なのは、保護者の不安や疑問に対する適切な情報を提供しておくこと。
料金体系、講師陣の情報、具体的な指導方針など、判断に必要な情報をわかりやすく提示することで、問い合わせへのハードルを下げることができます。
| チェックポイント | 改善ポイント | 効果 |
| 問い合わせ手段 | 複数チャネルの用意 | 接触機会を増加させる |
| 情報提供 | FAQを充実させる | 不安を解消する |
| 初期費用 | 明確な料金表示 | 信頼性を向上させる |
5. キャンペーンを実施する
効果的なキャンペーンは、潜在的な興味を具体的な行動に変える重要なきっかけに。
入会金無料や初月授業料割引といった特典に加え、教材プレゼントや個別カウンセリングなど、付加価値の高い特典を組み合わせることで、より強いアピールが可能です。
また、「期間限定」という要素を加えることで、検討中の保護者の背中を押す効果も期待できます。
特に、学期開始前や定期テスト前など、学習塾への関心が高まる時期に合わせたキャンペーンを設計しましょう。
6. 体験授業・無料相談を実施する
無料体験や個別相談は、塾の質を直接感じてもらえる重要な機会。
生徒の現状を丁寧に把握し、具体的な学習プランを提示することで、入塾への不安を解消できます。
また、保護者向けの個別相談では、教育方針や指導方法の詳細な説明に加え、家庭での学習サポート方法など、実践的なアドバイスを提供することで、塾の専門性と信頼性を示すことができます。
問い合わせ後の入塾率が低い場合
問い合わせや体験授業までたどり着いているにもかかわらず、最終的な入塾に結びつかないケースは、塾の本質的な価値訴求に課題がある可能性が高いです。
この状況を改善するためには、自塾の強みの再定義や、入塾に向けた不安解消のための具体的なアプローチが必要となります。以下の2点が改善策として挙げられます。
- 塾の強みを整理しなおす
- 入会特典を用意する
7. 塾の強みを整理し直す
入塾率の低さは、競合との差別化が不十分であることが一番の理由であることが多いです。
POF(他塾に比べ劣っている点)とPOD(独自の強み)を明確に整理し、なぜ自塾を選ぶべきなのかを具体的に説明しておきましょう。
例えば、「少人数制」や「個別指導」といった他でもありそうな特徴ではなく、「独自の教材を開発している」「医学部受験に特化している」など、具体的かつ独自の価値を明確にする、といった具合です。
差別化ポイントの例
- オリジナルの指導メソッドがある
- 講師研修システムが充実している
- 独自の学習管理システムがある
- 柔軟に振替できる
具体例や成果とともに説明して、より説得力のある提案にしていきましょう。
8. 入会特典を用意する
入会特典は、入塾の最終的な後押しとして重要な役割を果たします。
できれば学習効果に繋がるようなものが好ましいですが、単なる入会金免除や割引でもひとまずは問題ありません。
塾の生徒集めに適した時期は?
家庭内で学習塾の検討が行われやすい時期を理解し、プロモーションを効果的に行っていくことも重要です。ここでは生徒集めに適した時期として、以下の3つのタイミングについて解説していきます。
- 定期テストの後
- 長期休みの前(夏期・冬期講習へ)
- 2・3年生に上がるタイミング
定期テストの後
定期テスト後は、成績表をきっかけに多くの家庭で学習塾の利用が検討されます。
「思うように成績が伸びていない」と感じた保護者は、学習環境の改善を真剣に考えるタイミングとなるためです。
中間テスト後は次の期末テストでの挽回を期待して、また、期末テスト後は次の学期に向けた対策として塾への関心が高まります。
このタイミングでの訴求では、「なぜ思うような結果が出なかったのか」「どうすれば改善できるのか」という具体的な解決策を示すことが重要です。
例えば、無料の学習診断を実施し、弱点の分析と具体的な対策を提案することで、入塾への動機付けを高めることができるでしょう。
また、定期テスト対策講座などの講習を用意することで、まずは短期的な成果を実感してもらい、その後の継続的な入塾につなげていくというアプローチも効果的です。
テスト返却から1-2週間が最も反応の高い時期となるため、この期間に重点的なプロモーション活動を展開していきましょう。
長期休みの前(夏期・冬期講習へ)
長期休暇前は保護者が「この期間を有効活用したい」「遊びすぎないか心配」といった不安を感じやすい時期です。
夏期講習は新学期に向けた学習の立て直しの機会として、また、冬期講習は学年末・入試に向けた追い込みの時期として、保護者・生徒から位置づけをされていると考えておきましょう。
| 講習 | 訴求の仕方 | アプローチ時期 |
| 夏期講習 | 苦手科目を克服しよう | 6月中旬~ |
| 冬期講習 | 入試対策・学年の総復習をしよう | 11月中旬~ |
まずは講習会で具体的な成果を実感してもらい、その後の継続的な学習がいかに重要であるかを理解してもらうことで、自然な形での入塾につなげることができます。
2・3年生に上がるタイミング
学年の変わり目、特に中学2・3年生への進級時期は受験を意識し始めることから、塾選びが本格化するタイミングです。この時期は、期末テストの結果と新学年への不安が重なることで、学習塾への関心が特に高まります。
進級時の主な不安要素
- 難しくなる学習内容に対応できるのか
- 受験への準備が足りないのではないか
- 新学年で成績を維持できるのか
- 志望校選びがきちんとできるのか
こういった不安に対して、具体的な学習計画と目標を提示することで、入塾への動機付けを強めることができます。
「生徒が集まらない」と失敗するケース
生徒集めに失敗する塾には、いくつかの共通した特徴が見られます。
これらの失敗パターンを理解し、事前に対策を講じることで、効果的な集客が可能となります。以下の3つが代表的なケースです。
- 「教え方が上手ければ集客できる」と思い込んでいる
- 競合と似たような強みで選ぶ理由がない
- 教育の質が低く悪い口コミが広がっている
「教え方が上手ければ集客できる」と思い込んでいる
優れた指導力は塾の重要な要素ですが、それだけでは生徒は集まりません。
実際には、教え方の上手さを保護者や生徒に伝える工夫や効果的な集客など、総合的なアプローチが必要です。
競合と似たような強みで選ぶ理由がない
「少人数制」「個別指導」といった、他塾と同じような特徴だけを訴求している塾は、選ばれにくい傾向にあります。
重要なのは、自塾ならではの独自性を見出し、それを明確に伝えることです。
他塾と差別化できる要素としては、独自の指導メソッドがある、講師陣に特徴がある、サポート体制が充実している、教材に独自性があるなどが考えられます。
これらを具体的な事例や数値とともに示すことで、選ばれる理由を作ることができます。
教育の質が低く悪い口コミが広がっている
最も深刻なパターンは、提供している教育の質が低く、それが口コミで広がっているケースです。特にSNSや口コミサイトでの評判は、新規入塾検討者の大きな判断材料となります。
一度広がった悪評の回復には時間がかかりますが、以下のような取り組みが効果的です。
- 指導方法の見直しと改善を行う
- 講師研修を強化する
- 改善事例を積極的に発信する
集客に失敗したくないならトライプラス
少子化が進む一方で、個別指導塾への需要は着実に高まっています。
しかし、独力での運営にはあまりにも多くの課題があるでしょう。トライプラスなら、経営課題の解決を全方位でサポートしてもらいつつ開業していただくことが可能です。
全国知名度99%を誇る「トライ」の圧倒的なブランド力をベースに、開業リスクの小さい個別指導塾というビジネスを展開していただけます。
開校時には最大100万円の広告費用を本部が負担したうえで、リスクを最低限に抑えた上でスタートすることも可能です。興味がある方は、ぜひお問い合わせください。