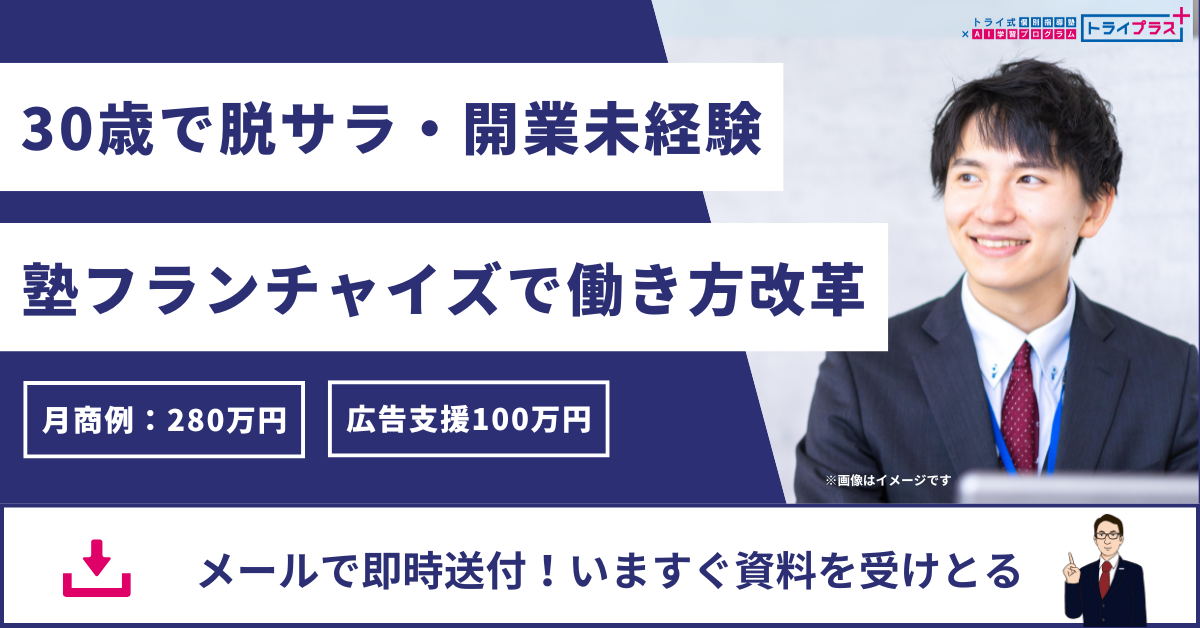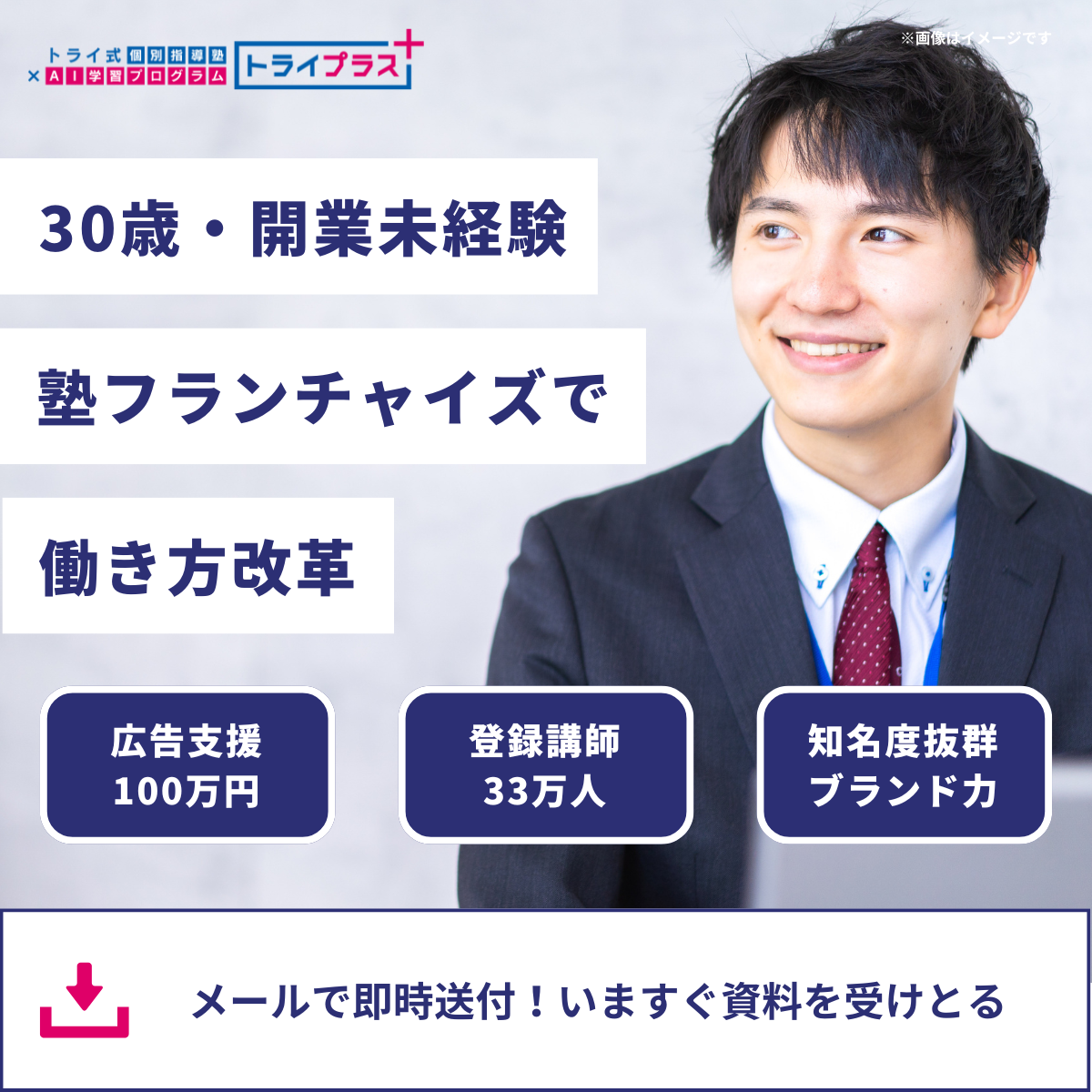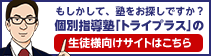塾の独立を成功させる方法!よくある失敗3つと雇われ塾長との違い
フリーランスをはじめ働き方が多様化した現代では、企業に所属する会社員から独立する人も珍しくなくなりました。
しかし、いざ自分が独立をしようとすると何から手をつければ良いかわからないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、学習塾の独立を検討している人に向け、方法やメリット・デメリット、準備をするものや流れについて解説していきます。よくある失敗や対策、成功させるための鉄則も合わせて紹介。
学習塾の開業を目指している人はぜひ参考にしてみてください。
- 塾の独立を成功させる方法
- 塾長として独立するメリット・デメリット
- 塾の独立に向けて準備するもの
- 塾長として独立開業する流れ
- よくある失敗と対策
- 塾の独立を成功させるための鉄則
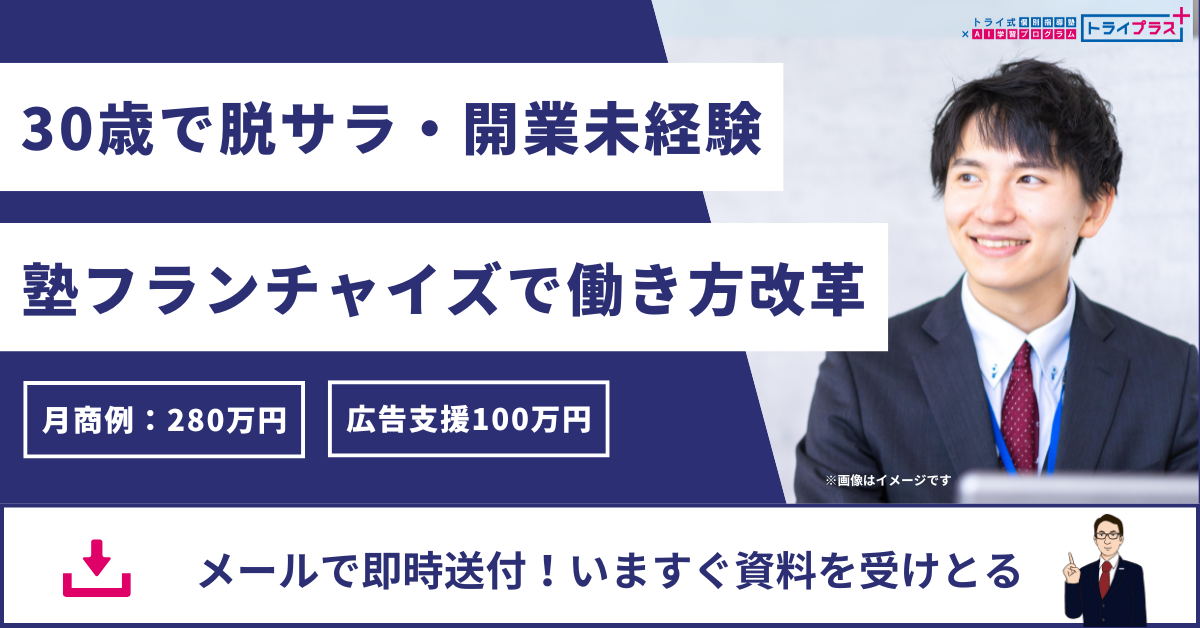
塾経営で独立する方法
学習塾の経営をするためには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、塾経営で独立するための方法を3つ紹介していきます。
1. 個人で塾を開業する
まずは個人・独力で塾を開業する方法です。
個人で塾を開業する方法のメリットには、以下が挙げられます。
- 柔軟な教育スタイルを構築できる
- 運営の自由度が高い
- コストを抑えることが可能
一方、次のようなデメリットも存在します。
- 生徒募集や集客を自分で行う
- 経営リスクと責任
個人で塾を開業する方法は自分のスタイルで塾を運営することができる反面、経営や集客などの業務を全て自分で行わなければなりません。
小規模で始められる点や、コストを抑えた運営が可能な点がメリットですが、持続的な生徒募集と経営のバランスを取るための努力が求められます。
2. フランチャイズで開業する
フランチャイズで学習塾を開業する方法は、既に確立されたブランドや運営システムを活用して、塾経営を始めるスタイルです。
主なメリットには、次のものが挙げられます。
- 既存ブランドの活用
- サポート体制
- 成功確率が高い
フランチャイズ本部から提供されるノウハウやサポートを受けながら、自分の地域で塾を運営することができるため、個人で一から開業するよりも成功の可能性が高く、安定した運営が期待できます。
一方で、フランチャイズで開業するには、次のようなデメリットもあるため注意が必要です。
- 自由度が低い
- 初期費用とロイヤリティが発生する
フランチャイズで塾を開業する方法は、独自でゼロから経営をするリスクを抑え、既存の成功モデルを活用しながら、安定した塾経営を行いたい人にとって効果的な選択肢です。
ブランド力と本部のサポートがあるため、初めての経営者でも安心して運営を開始できる一方、一定の費用や運営方針の制約があるため、自身の経営スタイルと合致するかをよく検討する必要があります。
3. 今働いている教室を買い取る
今働いている教室を買い取るという選択肢は、既に勤務している学習塾をオーナーから引き継ぐ形で独立する方法です。
この方法のメリットには、次のものが挙げられます。
- 既存の生徒と収益を維持できる
- 運営ノウハウやシステムをそのまま利用できる
- 信頼関係の引き継ぎ
上記のほかにも、教室をそのまま活用できるケースが多いため、学習環境の構築を行わなくて済む魅力もあります。
しかし、その一方で次のようなデメリットもあるため、注意しなければなりません。
- 資金が必要
- 現オーナーとの交渉が難しい
- 既存の運営システムに制約
今働いている教室を買い取る方法は、既存の環境を活用してリスクを抑えながら独立するための有効な手段です。
既に築かれた生徒や保護者との関係や運営ノウハウを引き継ぎ、スムーズに塾経営をスタートできる点が大きなメリットですが、既存の教室のシステムやカリキュラムに慣れてしまっている場合、独自の運営スタイルに変えようとすると、講師や生徒が反発される恐れもあります。
こちらの方法では、買い取りに必要な資金の準備やオーナーとの交渉が成功の鍵といえるでしょう。
塾長として独立するメリット・デメリット
塾長として独立するメリット・デメリットには、どのようなものが挙げられるのでしょうか。
それぞれをきちんと把握し、開業後に後悔しないようにしましょう。
最大のメリットは自由であること
塾長として独立する最大のメリットは、自由であることです。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 独立することで、自分自身の価値観や教育理念に基づいた塾の運営ができる
- 独立塾長として、授業の時間割や年間スケジュールを自分で決定できる
- 生徒の入塾基準やクラスの構成も自由
- 塾の料金体系も自由
- 塾の場所や規模も自分で決めることが可能
結果として、家庭や個人のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能になります。
雇われ塾長の場合、固定された時間割や方針に従う必要があることが多いですが、独立することでそれら制約がなくなることは大きなメリットであると言えるでしょう。
最大のデメリットは責任が大きいこと
自由度が高い一方で、塾長として独立するには「責任が大きい」ことがデメリットとして挙げられます。
具体的には、以下が挙げられます。
- 全ての意思決定に責任がある
- 経営を軌道に乗らないと収入が不安定になるリスクがある
- 従業員を雇用する場合、スタッフの管理や労務に関する責任も伴う
このように、塾長として独立すると様々な責任やリスクを負うことになります。
経営を軌道に乗せることができなかった場合、塾が閉鎖の危機に陥るだけではなく、開業に借り入れがあれば返済に追われることもあるでしょう。
また、雇用している講師やスタッフがいれば、従業員の生活を守る必要もあるため、多くのプレッシャーも感じることになります。
塾の独立に向けて準備するもの
ここでは、塾の独立に向けて準備するものを解説していきます。
準備1. 開業資金(約500万円)
塾の開業には、500万円程度の初期投資が必要です。
内訳には、理由は次のようなものが挙げられます。
- 物件費用:教室を借りるための敷金・礼金、家賃などの費用
- 内装や設備費:教室の内装工事や、机、椅子、ホワイトボード、照明、エアコンなどの設備の購入や設置費用
- 教材費:教材やテキストを仕入れるための費用
- 宣伝・広告費:生徒を集めるための広告やチラシ、ウェブサイト作成費用
- 運転資金:塾が軌道に乗るまでの間、家賃や人件費、教材費などの運営コストを賄うための資金
個人で資金を調達するのが難しい場合、金融機関や助成金などの制度を活用することも検討しましょう。
準備2. 教育カリキュラムと教材
塾の運営において、教育カリキュラムと適切な教材の選定は、方向性を定めるためにも重要な要素です。
以下のような流れで進めていきましょう。
- 塾のターゲットとする学年やレベル(小学生、中学生、高校生、受験生など)を洗い出す
- 科目や授業の進行スケジュール、学習目標を明確にし、どのタイミングで何を教えるかカリキュラムを設定する
- 教材の選定・開発:市販教材を利用するか、独自に教材を作成するかを検討する
個人でカリキュラムの作成や教材の準備が難しい場合、大手・有名塾の教材が使えるフランチャイズを活用した開業も検討してみると良いでしょう。
準備3. 事業計画
塾の成功には、しっかりとした事業計画が不可欠です。
事業計画は、塾の運営方針や成長戦略を描くための指針。以下のようなことを行っていきます。
- 塾を通じてどのような結果を目指すのか、例えば地域での生徒数の拡大や志望校合格率の向上など、具体的な目標を設定する
- 塾のターゲット層(小学生、中学生、高校生など)、どのレベルの生徒を募集するのかを明確にし、それに合わせたマーケティング戦略を立てる
- 開業に必要な資金、運営にかかる費用(家賃、教材費、人件費、広告費)を計算し、どれだけの生徒が必要なのか、どの程度の収益が見込まれるかを具体的にシミュレーションする
- 生徒募集の方法(広告、ウェブサイト、SNS活用、口コミなど)や宣伝活動のタイミングを計画する
事業計画は経営の方向性だけではなく、融資を受ける際には提出も必要になる大切なもの。
内容に具体性があることはもちろん、矛盾が無いように作り上げましょう。
準備4. 備品や講師
塾運営に必要な物品や人材を準備することも重要です。
- 備品(机、椅子、ホワイトボード、プロジェクター、パソコン、プリンター、書籍、テキストなど)
- 採用(採用後の研修も含め)
備品の経費を抑えるためには、中古品の購入やリースの利用を検討することもおすすめです。
また、フランチャイズであるトライプラスでは、33万人いる登録講師の中から採用することも可能ため、求人媒体への広告費や手間などのコストを軽減もできます。
塾長として独立開業する流れ
塾長として独立開業するおおまかな流れは以下のとおりです。
- コンセプトと事業計画を立てる
- 開校エリアを絞り込む
- 物件を選定する
- 開校準備を進める
- 開校してさらなる成長を目指す
それぞれのステップについては以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
塾の独立でよくある失敗と対策
これから塾の独立を検討する際、誰しもが失敗したくないと考えていることでしょう。
塾の独立でよくある失敗と対策について解説していきます。
失敗1. 資金不足による経営難
資金不足による経営難の主な原因は、開業前の資金計画不足や運転資金の確保不足です。
具体的には、初期投資(設備費、宣伝費、物件費)や生徒募集が予想通りに進まない場合に、毎月の家賃や人件費などの運営費を賄えなくなることが挙げられます。
また、収益が安定するまでの間に資金が尽きてしまうケースも多く、特に開業後の数ヶ月がリスク期間とされているため注意が必要です。
対策:余裕のある資金計画を立てておく
資金不足による経営難への対策は、余裕のある資金計画を立てておくことが重要です。
具体的に、予想外の支出や収入の遅れに備え、十分な運転資金を確保しておくことなどが挙げられます。
例えば、開業後6ヶ月から1年程度の運営費をカバーできる資金を準備し、収益が安定するまでの期間に対応できるようにしておきましょう。
収入が少ない場合でも、経費を賄えるように慎重な資金管理を行うことも重要です。
失敗2. 集客ができない
学習塾の収入源は、生徒の月謝であるため、集客ができなければ、経営は立ち行かなくなります。
十分な集客ができない原因としては、効果的な宣伝やマーケティングの不足や塾の魅力が十分に伝わっていないことが挙げられます。
例えば、広告やウェブサイト、SNSでの情報発信が不十分だったり、ターゲットとする生徒層に合ったプロモーションを行えてなかったりする場合、興味を引けません。
また、他塾との差別化ができていないと、保護者や生徒が塾を選ぶ理由がなくなり集客に苦戦します。
会社員やフランチャイズの場合、プロモーションも確立しておりブランド力もあるため、ある程度の集客が見込めますが、独立するとそれらを失ってしまうのです。
対策:マーケティング計画を立てておく
学習塾の集客対策における「マーケティング計画を立てておく」ことは、ターゲット層を明確にし、効果的な集客方法を事前に計画することです。
具体的にはどの年齢層や学力レベルの生徒を対象にするのかを決め、それに合った広告やSNS、口コミ戦略を活用していきます。
また、地域の需要や競合塾との差別化を図り、塾の強みや魅力を明確に打ち出すことが重要です。
これにより、効率的に生徒を集めることができ、集客の失敗を防げます。
集客に対して不安を感じている人は、フランチャイズによるブランド力のサポートやPRのサポートを活用することも検討してみましょう。
学習塾の集客については、以下の記事も参考にしてください。
失敗3. 低単価で利益率が悪い
低単価で利益率が悪い一因は、授業料が低すぎるために収益が十分に上がらないことです。
他塾との競争を意識して授業料を安く設定しすぎたり、提供する教育サービスの価値に対して料金が適切ではなかったりする場合、利益が出にくくなります。
持続的な低価格を実現できるような仕組みがあればよいですが、原則として低価格にしても固定費(家賃や人件費)はそれほど変わらないため、利益率が圧迫され経営が苦しくなることがあります。
対策:競合と差別化し付加価値をつける
学習塾における「競合と差別化し付加価値をつける」とは、他塾にはない独自の強みやサービスを提供し、授業料に見合う価値を感じてもらうことです。
「他の塾とはどう違うのか」「子どもの未来はどう変わるのか」がイメージできるように強みを打ち出し、生徒や保護者に「この塾だからこそ通いたい」と思ってもらうことが重要です。
差別化できれば、価格競争を避けつつ適切な授業料を設定でき、利益率の向上が期待できるでしょう。
また、フランチャイズであれば大手・有名塾のブランドを活用できるため、それだけでも差別化を図ることが可能です。
塾の独立を成功させる5つの鉄則
学習塾に限らず、起業するにはリスクがつきもの。それでも、ポイントを押さえることでそれらを軽減することができます。
ここでは、塾の独立を成功させる5つの鉄則を解説していきます。
鉄則1. 事前の計画は綿密に立てる
塾の独立を成功させるための鉄則として、事前の計画を綿密に立てることは非常に重要です。
これには以下のような要素が含まれます。
- 塾の運営方針や目標を明確にし、短期・長期的な計画を立てます(事業計画の策定)
- 資金不足で経営が困難にならないよう、初期費用や運転資金をしっかりと確保する計画を立てます(資金計画の準備)
- 生徒を集めるためのマーケティング戦略を事前に練ります。ターゲットとなる地域や生徒層を調査し、それに合った広告方法を計画します(マーケティング計画の準備)
- 開業までの準備や、開業後の運営スケジュールを綿密に立てます(運営スケジュールの整備)
上記以外のように事前準備を行っても、予期せぬ事態が起こる可能性があります。
生徒数が予想より少ない場合、地域の競争が激化した場合など、様々なリスクを想定し、それに対する代替案や対策を事前に準備しておくとよいでしょう。
このように、綿密な事前計画を立てることで、予期せぬトラブルを回避し、経営が軌道に乗るまでの道筋をしっかり描けます。計画が具体的であればあるほど差異が生じた際の対応もよりクリアに考えられるため、塾の独立成功率が高まるでしょう。
鉄則2. 競合と差別化する
塾の独立を成功させるためには、競合と差別化することが重要です。
差別化には、以下のポイントが挙げられます。
- 特定のニーズに焦点を当て、中学受験専門や個別指導などで他塾との差別化を図る
- 少人数制、個別指導、オンライン学習など、独自の教育メソッドやカリキュラムを採用する
- 学習サポート以外にも、進路相談や自習環境など、付加価値のあるサービスを提供する
- 満足度の高いサービスで評判を向上させ、結果的に保護者や生徒に選ばれる存在になる
これらを実践し、他塾との差別化を進めることで、独立塾として成功する可能性が高められるでしょう。
鉄則3. 集客には力を入れる
塾の独立を成功させるために生徒を集めることが必要不可欠であり、そのためには集客に力を入れなければなりません。
集客におけるポイントには、以下のものが挙げられます。
- どの層を対象にするかをはっきりさせ、効果的なマーケティングを行う
- WebサイトやSNSで、塾の特徴や実績を発信し、認知度を上げる
- 紹介制度などを使って、保護者や生徒に口コミを広めてもらう
- 無料体験や模試などで、塾の魅力を直接伝える
- チラシ配布や地元イベントでの宣伝により、地域での知名度を高める
- 合格実績や成績向上の具体例を示し、信頼を得る
これらの施策で効果的な集客を行うことが、独立塾の成功に繋がります。
しかし、独立したてのタイミングでは実績がなく、アピールできる材料が不足することもあるでしょう。
そのような場合には、フランチャイズのブランド力や実績を活用することもおすすめです。
鉄則4. 優れたカリキュラム・指導法を確立する
優れたカリキュラム・指導法を確立することによって、生徒が成果を出し、塾の評判を高めることができます。
以下のポイントが重要です。
- 各学年や科目ごとに達成すべき学力や目標を設定し、体系的なカリキュラムを作る
- 生徒一人ひとりの学力やペースに合わせた指導を行い、効果的な成績向上を図る
- わかりやすい解説方法を講師陣ができるように教育する
上記は一例ですが、優れたカリキュラムと指導法を提供できることをアピールすることによって、顧客となる生徒や保護者から通塾することへの意欲を高める効果が期待できます。
アピール内容は、生徒が「通いたい」「目標が達成できそう」と感じてもらえるよう、工夫すると良いでしょう。
鉄則5. 保護者と信頼関係を築く
保護者の信頼を得ることで、長期的な生徒の確保や紹介の増加に繋がります。
成績の向上は直ぐに効果が実感できないことが普通ではありますが、通塾してから数ヶ月で「成果が出ていない」とクレームを受けてしまう可能性があります。
定期的なコミュニケーションを取ることによって、生徒がどのような取り組みをしているかが可視化され、保護者は安心感が得られるため、クレームの発生を予防することが可能です。
信頼関係を築き、塾の評判が高まると生徒や保護者間での口コミによって、生徒の新規入会増加にも期待できます。
会社員の塾長と独立した塾長の違い
これから開業しようとしている人は、会社員の塾長と独立した塾長の違いについて理解をしておく必要があります。
ここでは、会社員の塾長と独立した塾長の違いを解説していきます。
年収の幅が違う
会社員の塾長の場合、一般的に所属企業の給与体系に基づく固定給が多く、年収は安定しています。
しかし業績や成果に応じたボーナスがある場合も、給与の増減はそれほど大きくなく、一定の範囲に収まる傾向があります。
一方の独立した塾長は、成功すれば高い収益を得る可能性があり、年収は上限がありません。
しかし経営が軌道に乗らなければ、収入が少ない、もしくは赤字になる可能性もあります。
だからこそ、独立する場合は入念な準備が必要になるのだと言えます。
業務と責任の範囲が違う
会社員の塾長と独立した塾長では、業務と責任の範囲が違います。
会社員の塾長の場合、基本的に塾運営の一部を担当することが多いです。
具体的には、授業の管理や講師の指導、保護者対応が主な業務で、経営的な責任は本部や経営陣が負います。
給与や経費、設備管理などの細かい経営面は担当外のことが多いです。
一方、独立した塾長はすべての業務を管理し、経営の全責任を負います。
授業やカリキュラムの作成、講師の採用・育成に加えて、集客、経理、設備管理、経営戦略まで、塾のあらゆる面を自ら統括する必要があります。
自由度が違う
会社員の塾長は、会社の方針やルールに従って運営します。
カリキュラムや指導法、マーケティング戦略なども、会社の決定に基づくため、自分の裁量が制限されることが一般的です。
一方、独立した塾長は自由度が非常に高く、自分の塾の方針やカリキュラム、指導法、集客方法をすべて自由に決定できます。自分のビジョンに基づいた塾運営ができる一方で、その責任もすべて自分にかかってくるということです。
学習塾の独立についてよくある質問
いざ塾独立をしようと考えた際、様々な疑問が湧くものです。
ここでは、学習塾の独立についてよくある質問に対しQ&A形式で解説していきます。
会社員の塾長が独立したらどうなる?
会社員の塾長が独立すると、以下のような変化が生じます。
- 収入が不安定になるが、成功すれば大幅に増加する可能性がある
- 業務と責任が全て自分に集まる
- 自由度が大幅に増える
まず、独立することによって固定給がなくなり、塾の経営状況によって収入が大きく変動します。
成功すれば収入が大きく増える一方で、安定しない時期もあるため準備金が重要です。
また、責任面においても経営・授業・集客・経理など、塾の運営に関する全ての業務と責任を自分で負います。
成功も失敗もすべて自己責任となるため、プレッシャーも大きくなると言えるでしょう。
そのほか、カリキュラムや運営方針・指導法など、全てを自分の判断で決定できるため、自己のビジョンに基づいた塾運営が可能になります。
塾の経営者の年収はいくら?
気になる収入面ですが、塾経営者の平均年収は800万円程度といわれています。
日本の給与所得者の平均年収は461万円であることから、高い水準にあるといえるでしょう。
しかし開業したばかりのタイミングでは、集客がうまくいかず、収入が会社員時代よりも減る可能性もあります。
独立後、スタートダッシュをするために、独立前から開業する旨の告知をするといった工夫をしてみましょう。
学習塾を開業するにはいくら必要?
学習塾を開業する際に必要な資金は、規模や地域、形態によって異なりますが、一般的には500万円程度が目安と言われています。
主な費用項目は以下の通りです。
- 物件費用:賃貸契約の初期費用や保証金など
- 内装・設備費用:机、椅子、ホワイトボードなど
- 教材・備品費用:教材、プリンター、文房具など
- 広告・集客費用:チラシ、ウェブサイト、SNS広告など
- 運転資金:数ヶ月分の家賃や光熱費など
小規模な自宅塾やオンライン塾、講師が不要な映像塾などであれば、初期費用を抑えることも可能です。
安全に独立するならトライプラスのフランチャイズ
塾の経営には様々なリスクが伴いますが、フランチャイズの活用はリスクを軽減する有効な選択肢の一つです。
トライプラスは、日本最大級の個別指導塾フランチャイズとして、オーナーの開業をトータルでサポート。
全国知名度99%を誇る「家庭教師のトライ」のブランドを使った集客に加え、教育ノウハウの提供、人材採用など経営の様々な場面で力強くバックアップします。
多くの教室が1年目から黒字化を実現している実績もあり、未経験からでも安心して開業していただけます。
独立開業やフランチャイズ加盟に関心をお持ちの方は、ぜひ一度トライプラスにご相談ください。